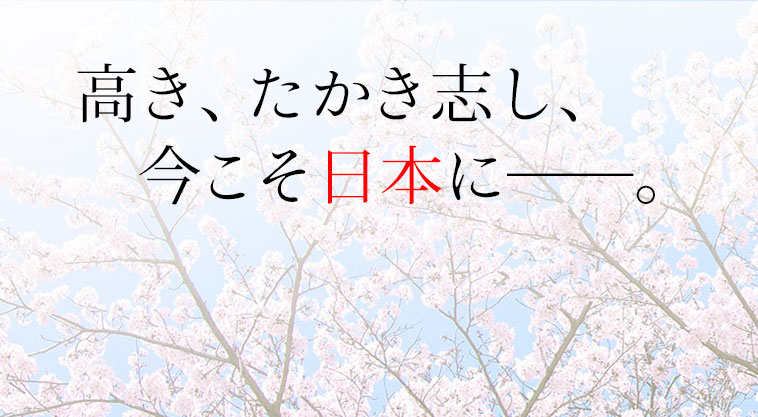最新の記事一覧
-
12月31
-
2022/12/31【米民主共和両党がウクライナ支援継続で一致している訳ではない理由とは】
-
ウクライナのゼレンスキー大統領が電撃的に訪米し、連邦議会で演説したのは記憶に新しいところです。 日本での報道では、演説が民主共和両党から好意的に受け入れられたと、押しなべて伝えられていました。 この報道だけを見ると、「米国はウクライナ支援で一致しているのだな」と思ってしまう人が多いと思います。 しかし、実際には同氏の演説は、共和党の下院議員の約6割が欠席していました。 これは、多くの共和…
-
12月26
-
2022/12/26【秘密保護法をめぐる矛盾とは】
-
自衛隊の現役幹部が、特定秘密保護法で定められた機密を漏らしたとして懲戒免職されました。 特定秘密保護法違反による初めての処分ということになります。 特定秘密保護法は2014年に施行されましたが、それまではこの種の法律が事実上無かったため、諸外国に比べて日本はスパイ天国と言われる状態でした。 特定秘密保護法も、スパイを防止するうえで万全とはいえないものの、その施行により米国など同盟国…
-
12月24
-
2022/12/24【長引くウクライナ戦争がもたらす別の弊害とは】
-
2022年の世界のトップニュースをあげるとしたら、ウクライナ戦争がその一つでしょう。 ウクライナ軍は、欧米の援助により予想に反して善戦し、一部地域ではロシア軍を押し戻しています。 逆に言うと、ロシア軍は思ったほど強くないとのレッテルを貼られてしまいました。 こうした状況から、欧米が直接戦闘に参加すれば、簡単にロシアに勝利できるとの見方が浮上しましたが、それを阻止しているのがロシアの核兵…
-
12月21
-
2022/12/21【電気自動車の導入前に留意すべきこととは】
-
住宅にソーラーパネルを設置して、電気自動車(EV)を蓄電池として利用すれば、効率的に再生可能エネルギーを利用できるとの考え方があります。 一部の左翼メディアは、脱原発と脱炭素を推進する文脈の中で、こうした考え方を後押ししているのを見かけます。 確かに、ソーラーパネルは夜間などに発電効率が低下するため、外部電力への依存度を減らすには蓄電池と組み合わせる必要があり、蓄電池はコストが高いため、EV…
-
12月20
-
2022/12/20【財源だけではない国防強化の課題とは】
-
知人のビジネスマンが、ある製品を作成するために国内の縫製工場を探したところ、引受手が見つからず困っていました。 少し複雑な製品であるものの、20年ほど前ならば、どこでも引き受けてくれたにもかかわらず、今では縫える熟練工がほとんどいないとのことでした。 どうやら国内の縫製工場が次々に海外移転し、それに伴い国内の技術継承が上手く行っていないようです。 そのビジネスマンも、「今じゃ日本より中国の…
-
12月14
-
2022/12/14【今年の漢字発表に見る宗教家の役割とは】
-
師走の恒例、今年の漢字が発表され、今年は「戦」とのことでした。 選出の理由として、物価高やワールドカップもあがりましたが、ウクライナでの軍事衝突のインパクトが大きかったようです。 発表後、関西にある伝統宗教の宗教家が、大手マスコミのラジオ番組に出演し、「戦」が選ばれたことに対する感想などを聞かれ答えていました。 その中で、今年はウクライナでの戦闘で多数の犠牲者が出ていることや、幼稚園で痛ま…
-
12月12
-
2022/12/12【先見性を持っているのはどこか】
-
2022年も残りわずかですが、今年は世界が一層不安定化しました。 良くも悪くも世界情勢に大きな影響を与える国の一つは米国ですが、昨年初めに就任したバイデン大統領は、分断された世界を一つにすることを掲げでいました。 米国だけでなく大半の日本のマスコミも、トランプ大統領の時代は分断が進み、バイデン氏なら問題が解消するという考えに同調し支持していたように記憶しています。 しかし、現実は、ウク…
-
12月08
-
2022/12/9【地獄の存在とは】
-
少しシリアスな映画やマンガなどで、「地獄に堕ちろ」というフレーズを目にすることがあります。 映画やマンガの製作者が地獄についてどの程度の理解を持っているのか定かではありませんが、このフレーズは、多くの場合、気に入らない相手を「拒絶する」という意味で使われており、「地獄」そのものを深く考察しての言い回しでない場合がほとんどです。 あくまでも、エンターテイメントの中の表現の一つのように捉えられて…
-
12月06
-
2022/12/5【中国の民主化の兆しとは】
-
現在、中国ではかつてない規模で民衆によるデモが行われています。 当初は、厳しすぎるゼロコロナ政策に対するデモと見られていましたが、次第に民主化を求めるデモの色彩を帯びつつあります。 当局は、スマホの位置情報で追跡したり、街頭の監視カメラによる顔認証を駆使したりして、取り締まりを強化しています。 一方、民衆の側は当局の摘発を逃れるため、言論統制に抗議する意味を込めて何も書いていない白…
-
12月03
-
2022/12/03【世界の核兵器の現状とは】
-
中国が保有する核弾頭数は、現在400発から、10年後には1500発に増加する見通しであると米国防総省が発表しました。 米ロはそれぞれ、5000発から6000発保有しているので、中国は数の面ではまだまだ及びませんが、米ロの核弾頭は製造から数十年経過した旧式のものも少なくないことから、最新型をハイペースで量産する中国には一層の警戒が必要です。 また、国連常任理事国5か国以外にも、インド、パキスタ…