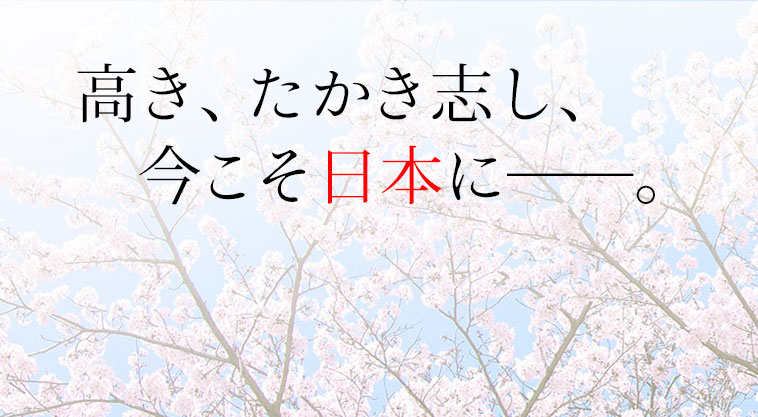最新の記事一覧
-
5月18
-
2019/05/18【同じ民主主義国家である台湾との関係強化を】
-
台湾は、議会制民主主義をとっており、一党独裁の専制主義国家とも言える中国とは、事実上、別の国家として成り立っています。 これに対し、中国は、台湾の独立を許さないとして、政治的に圧力をかけるとともに、経済的にも取り込もうとしています。 ただ、中国共産党政府は、過去一度も台湾を統治した事実はありませんから、台湾は独立するまでもなく、既に独立した国家と言えます。 「台湾は中国の一部」というの…
-
5月17
-
2019/05/17【中東が不安定化すれば原発に頼らざるを得ない】
-
イランを中心とする中東情勢が緊迫化しています。 日本の総発電量のうち8割以上を火力発電が占めていますが、その火力発電に使う化石燃料のほぼ全てを湾岸地域などの海外からの輸入に頼っています。 従って、中東情勢次第では、輸入が滞る事態を想定しておかなければなりません。 しかし、化石燃料の備蓄には限りがありますし、再生可能エネルギーの発電割合をどんなに増やしたとしても、火力発電の分を賄うことは…
-
5月16
-
2019/05/16【悪事を犯させないための抑止力】
-
5月15日は沖縄が本土に復帰して47年目となった日です。 本土復帰後も米軍基地が多く残り、基地負担は減りつつあるとはいうものの、先の大戦で悲惨な地上戦を経験した沖縄として、基地負担を軽減するよう求める声も理解できない訳ではありません。 ただ、「平和のためには沖縄県に基地を含め一切の軍事的なものはいらない」という主張には疑問を感じます。 確かに、軍事力が一切無ければ、軍事衝突など起こり得ない…
-
5月14
-
2019/05/15【中国に自由、民主、信仰の価値観を広めるのが宗教の使命】
-
中国紙の1面にローマ法王庁の国務長官のインタビューが掲載されました(※)。 インタビューでは、同長官が中国を持ち上げた上で、更なる関係改善を進める意欲を示したとのことです。 中国共産党員には信仰が禁じられ、国民には信教の自由が認められていない中国は完全な無神論国家を目指しています。 その中国とローマ法王庁は、司教の任命権をめぐり長年対立してきましたが、昨年、ローマ法王庁側が折れる形で和…
-
5月14
-
2019/05/14【消費“減”税で好景気を】
-
景気動向指数が6年ぶりに「悪化」となりました。 国民の間に景気回復の実感が無いまま、日本の景気は後退局面に入ろうとしています。 ですから、国民の所得が実質的に増えない中での消費増税は、文字通り消費にブレーキを掛けることになり、このままでは景気が悪化します。 消費増税は、モノやサービスの値段が一斉に上がるようなものですから、所得に変化が無いのであれば、買えるものが少なくなるのは当たり前のこと…
-
5月13
-
2019/05/13【農業を未来産業とするには】
-
G20の農業担当閣僚会合が開催され、人口増加に対応するための農業の生産性向上などを盛り込んだ閣僚宣言を採択しました。 今回の会合について日本国内では、福島県産農産物の輸入規制撤廃について如何に理解を得られるかに注目が集まっていましたが、世界では、増え突ける人口に対して如何に食料を安定供給できるかが課題となっていたので、日本と世界とでは少し温度差があったようです。 日本では、農業の就労…
-
5月12
-
2019/05/12【生産拠点の脱中国化を進める時】
-
米中の貿易交渉は難航している模様です。 米国は、中国からのほぼ全ての輸入品に関税を上乗せする手続きを開始し、中国も対抗措置を取るとしています。 報道の中には、「自由貿易を堅持したい中国と、自国ファーストで保護主義の米国」といった構図で語られているものもありますが、少なくとも中国は相互主義に基づく対等な自由貿易の国ではないのではないでしょうか。 なぜならば、中国による外国企業に対する強制的な…
-
5月10
-
2019/05/11【保育無償化は体の良いバラマキでは?】
-
幼児教育と保育を無償化する法案が成立しました。 政府・与党などは、無償化で子育ての負担を軽減し、少子化に歯止めをかけることができるとしています。 確かに、子育てに掛かる費用が少なくないことから、2人目、3人目などと本当はもっと子供が欲しいのに、断念する家庭もあることは事実でしょう。 しかし、幼児教育と保育の無償化の費用は年間7千7百億円余りと見積もられており、費用に見合った少子…
-
5月10
-
2019/05/10【米中貿易戦争でトランプ大統領と共闘を】
-
米中貿易戦争が激化する様相を呈しています。 トランプ大統領は、「中国が貿易交渉を長引かせ、民主党政権に交代することを期待しているが、そうはいかない」とツイートしています。 これは、米中貿易交渉の過程で、中国に進出した外国企業に対し強制的に技術移転を求める法律の改正に一旦は合意しながら、その後、中国側が撤回したことを指しているものと思われます。 そしてトランプ大統領は、中国からの輸入品に課し…
-
5月07
-
2019/05/07【問われるニュージーランドの安全保障政策】
-
産経新聞に「第3列島線」なる言葉が取り上げられていました(※)。 「列島線」は中国の軍事上の防衛ラインと位置付けられており、従来から言われている第1列島線は、日本列島から台湾、南シナ海に続くもので、同様に第2列島線は、日本列島からグアム、ニューギニア島に続くとされます。 そして、今回の第3列島線は、概ねハワイからニュージーランドを結ぶもののようです。 これらの列島線は、中国の覇権拡大を…