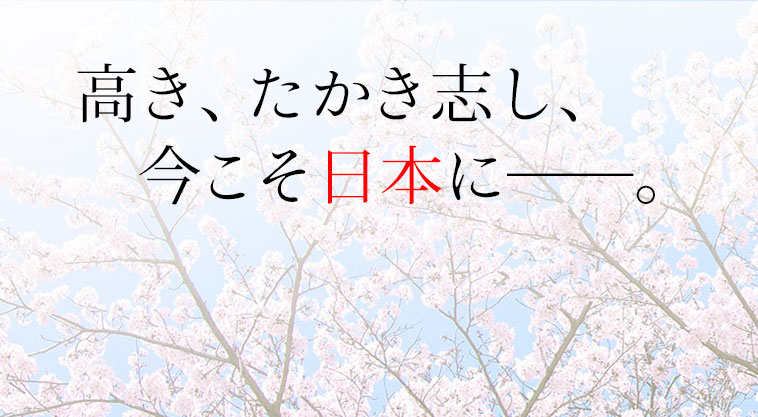最新の記事一覧
-
7月27
-
2020/07/27【中共による尖閣諸島侵攻の脅威が高まる】
-
台湾周辺で中国軍の動きが活発化しています。 外国の複数のメディアは、中国軍が台湾進攻の準備を進めていると指摘しています。 実際、台湾軍は今月に入って高度の警戒態勢を敷いている模様です。 もともと中国共産党(中共)にとって台湾統一は悲願ですが、ここにきて習近平政権が台湾進攻に踏み切る理由として、経済政策の失敗、新型コロナウィルスの感染拡大、中国南部での大洪水などから、国民の目を逸らし政権…
-
7月26
-
2020/07/27【霊的人生観を前提とした医療サービスを】
-
ある知人のご家族は、重い認知症で療養しています。 その方は脳の萎縮が進行し、言語を喪失するなど意思表示をすることはなく、全介護状態になっているとのことです。 そうなると、看護や介護の担当の方の中には、意思表示ができる患者に比べて対応が明らかに異なる人がいて、患者の家族としては複雑な思いがあると話しておられました。 看護や介護の現場は、ただでさえ非常に忙しい上に、コロナ禍で感染防止に大変な緊…
-
7月24
-
2020/07/23【これから必要となる“人の温もりの経済学”】
-
コロナ禍で人と会う機会が減っています。 テレワークの導入拡大により、対面ではなくテレビ会議で他人と話すようになったというのはまだいい方で、メールやチャットにより業務の指示や報告をするようになったという声も多く聞きます。 そうなると、同じ職場内でもお互いの信頼関係が気薄になります。 一般に日本人は買い物時に店員と話すことは元々そう多くありませんが、感染拡大によりその会話さえも必要最小限に…
-
7月22
-
2020/07/22【この状況で最低賃金のアップはどうなの!?】
-
今年度の最低賃金を議論する厚労省の審議会は、労使間の隔たりが大きく紛糾しました。 コロナ禍で業績が低迷する企業側は賃金アップを容認できませんし、一方の労働者側はコロナ禍であるからこそ生活を守るために賃金アップが必要ということでしょう。 どちらの主張も理解できる部分はあります しかし、政府が示す最低賃金が実際の賃金になっている企業が少なくない中、そうした企業の多くが、持続化給付金、雇用調…
-
7月19
-
2020/07/19【親中派の多い現在の与党に危惧する】
-
自民党の国防議連は、尖閣諸島周辺で圧力を強める中国への対抗として、尖閣諸島での上陸調査や日米訓練の実施を政府に求めるとしています。 このままでは、日本の尖閣諸島実効支配を突き崩しかねない中国による既成事実の積み重ねを、座視することになりかねません。 ですから、日本の主権を守るために、自民国防議連のこうした動きを心強く感じるとともに、当然の動きであると思います。 ただ、対中国に関して…
-
7月18
-
2020/07/18【葬儀の簡素化傾向への危惧】
-
コロナ禍で葬儀の規模縮小が顕著になっているようです。 ある知人も先日葬儀を営む際に、故人は生前の親交が多い人だったにもかかわらず、感染を警戒した親族の意向で、少人数での家族葬を行わざるを得なかったとのことでした。 近年、若い世代や都会ほど葬儀を簡素化する傾向にあるようが、旧来の風習を大切にする高齢の世代や田舎の人々などの存在が一定の歯止めになっていたものの、コロナ禍で堂々と簡素化できるように…
-
7月18
-
2020/07/17【課税よりも高貴なる義務が繁栄をもたらす】
-
世界のミリオネア83名が、コロナ禍に対応するため自分たちに大幅な課税をするよう求める書簡を各国政府に送ったとのことです。 こうした動きに対して、殊勝な心掛けと称する声がある一方で、風当たりが強まる富裕層のパフォーマンスに過ぎないとの見方もあるようです。 では、自らに課税を求めることと、寄付や慈善事業を行うことには、どのような違いがあるのでしょうか。 例えば、世界的な大富豪であるビル・ゲイツ…
-
7月13
-
2020/07/13【食糧安全保障の強化を】
-
世界的なコロナ禍で、世界の食料供給体制が不安定化するとの指摘があります。 今のところ、例えば主要な穀物である小麦の市場価格が高騰するような状況になっていませんが、コロナ禍が農作物の生産量を押し下げる要素であることに間違いはなく、第2波、第3波次第では、輸出国がいつ供給を自国優先にしてもおかしくはない状況です。 そうした中、もう一つの要素として蝗害(こうがい)が心配されています。 蝗害と…
-
7月13
-
2020/07/12【憂慮すべきは防衛費ではなくバラマキ政策のほうでは】
-
米政府は、日本に対して最新鋭のステルス戦闘機「F-35」を105機(総額2兆4800億円相当)売却することを決めました。 売却額としては異例の規模となり、財政難の折、早速一部から批判の声も上がっているようです。 確かに、今回の契約は高額に見えますが、これらの費用は単年度で支払う訳ではありません。 政府は調達期間を明らかにしていませんが、1機約100億円の現在の主力戦闘機「F-15」は約…
-
7月10
-
2020/07/10【中国で外国人が恣意的に拘束される!?】
-
オーストラリア政府は、中国に渡航した際に恣意的に拘束される恐れがあるとして、自国民に中国への渡航を控えるように勧告したとロイターなどが伝えています。 これに対し中国は、「中国の法律を守る限り外国人を拘束することはない」などとして反発しています。 しかし、先に施行された香港版「国家安全法」では、外国人が外国で行った行為にも適用されると解釈できることから、少しでも中国政府と異なる見解を持つ外国人…